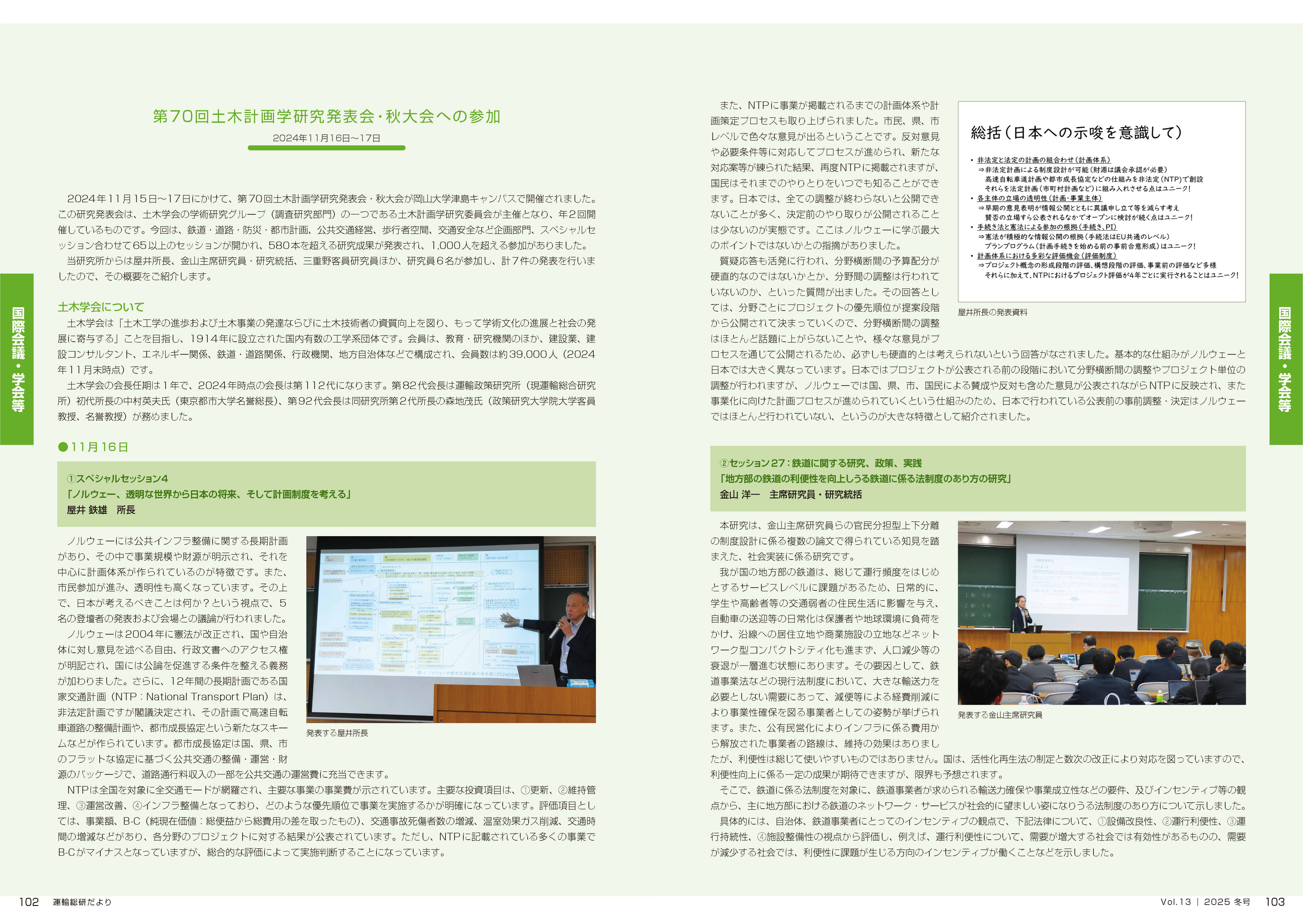第70回土木計画学研究発表会・秋大会への参加報告
- 他機関との交流


| 日時 | 2024/11/15(金) 〜 17(日) |
|---|
2024年11月15日~17日にかけて、第70回土木計画学研究発表会・秋大会が岡山大学津島キャンパスで開催されました。この研究発表会は、土木学会の学術研究グループ(調査研究部門)の一つである土木計画学研究委員会が主催となり、年2回開催しているものです。今回は、鉄道・道路・防災・都市計画、公共交通経営、歩行者空間、交通安全など企画部門、スペシャルセッション合わせて65以上のセッションが開かれ、580本を超える研究成果が発表され、1,000人を超える参加者がありました。
当研究所からは屋井所長、金山主席研究員・研究統括、三重野客員研究員ほか、研究員6名が参加し、計7件の発表を行いました。
《土木学会について》
土木学会は「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、1914年に設立された国内有数の工学系団体です。会員は、教育・研究機関のほか、建設業、建設コンサルタント、エネルギー関係、鉄道・道路関係、行政機関、地方自治体などで構成され、会員数は約39,000人(2024年11月末時点)です。
土木学会の会長任期は1年で、2024年時点の会長は第112代になります。第82代会長は運輸政策研究所(現運輸総合研究所)初代所長の中村英夫氏(東京都市大学名誉総長)、第92代会長は同研究所第2代所長の森地茂氏(政策研究大学院大学客員教授、名誉教授)が務めました。