第28回 日中運輸経済技術交流会議
- 国際活動
- 他機関との交流

| 日時 | 2025/9/24(水) |
|---|
開催概要
2025年9月24日、北京市内の中国科学技術会堂会議室で、第28回日中運輸経済技術交流会議を開催した。この会議は、1984年(昭和59年)以来、中国国家発展改革委員会総合運輸研究所(ICT)と国土交通省及び当研究所(JTTRI)との間で、運輸政策及び運輸事情全般に関する情報交換を目的として概ね毎年1回両国交互に開催し、今回は2024年7月東京開催に続くもの。
ICTから李連成所長を含む18名、JTTRIから宿利会長及び屋井所長を含む5名並びに国土交通省から米山国土交通政策研究所所長が、在中国日本国大使館後藤参事官の立会の下で参加した。
会議の冒頭、ICT李所長より開会挨拶として、歓迎の意とともに、42年間続く交流を深め、今回のテーマについて成果を共有していきたいと表明された。続いて、JTTRI宿利会長の開会挨拶では、ICTへ謝意を表した上で、少子化や高齢化、生成AIなど技術革新の活用、気候変動によって頻発化している災害あるいは新たな自然環境への対応という喫緊の課題において運輸交通分野は両国とも重要な位置を占めており、今回のテーマは国家的・地球的規模の課題として時宜を得たものであり、双方の情報や知見を共有して両国の課題を克服し、運輸分野の発展に貢献していきたいと期待を述べた。
その後3つの議題・テーマとして、「交通・物流と産業の融合」「都市圏の交通発展」「緊急物流(緊急物資輸送)」を設定し、各セッションで日中双方から研究調査発表と議論を行った。最後に、JTTRI屋井所長、ICT李所長からの閉会挨拶により終了した。
前日23日及び翌日25日は、ICTの案内により、北京市軌道交通指揮センター、北京西駅の見学と、北京地下鉄自動運転等の乗車体験を行った。次回は、2026年に日本で開催する計画である。
会場(中国科学技術会堂会議室)
当日の結果
会議の冒頭、ICTの李連成所長より開会挨拶として、歓迎の意とともに、42年間続く交流を深め、今回のテーマについて成果を共有していきたいと表明された。
続いて、JTTRIの宿利正史会長の開会挨拶では、開催の諸準備についてICTへの謝意を表明した上で、次の旨を述べた。
・日本が先行してきた少子化や高齢化に対応した運輸交通のあり方は、中国も今後同様の課題に直面していく一方で、生成AIなど技術革新の活用や、気候変動により頻発化する災害と新しい自然環境への対応という喫緊の課題において、運輸交通分野は両国とも重要な位置を占める
・運輸交通セクターは、国民生活の活力や持続可能な経済社会、都市・産業の国際競争力強化等へ貢献が求められており、会議の3つの議題は、国家的・地球的規模の課題として時宜を得たテーマ。双方の情報や知見を共有して両国の課題を克服し、運輸分野の発展に貢献していきたい

開会挨拶(李連成所長)

開会挨拶(宿利正史会長)
■セッション1「交通・物流と産業の融合」
ICTから賀振東研究員が「交通、物流と産業の融合」(原文は中国語)と題して発表した。中国では、運輸と物流は別概念として捉えていることを概説し、産業も含めて融合させることが必要であるとした上で、①端緒として、2009年に政府が公布した「物流業の調整・振興計画」が目指す物流企業の現代化、運輸と物流サービスの融合、②2019年公布の「交通強国建設要綱」が目指す「グリーンで効率的な物流システム」では、目標となる「国内当日着」「周辺国2日間着」「世界主要都市3日間着」、海陸空物流間の標準化、2024公布の「物流コスト低減行動計画」では、都市圏の産業集積と物流ハブによる臨空経済・臨港経済を目指す「国家物流ハブ経済区」(西安等)が紹介された。③今後の更なる発展の方向性では、「流通市場改革」を「物流・商貿両システムの発展」で推進し、「交通運輸、金融、信用サービス」の三者が支える政策概念が紹介された。
質疑では、日本側より、中国で「運輸と物流サービスの融合・一体化」が議論される背景として、両者の政府所管部門について質問があり、賀研究員より、運輸業は交通運輸部に一元化されているが、物流業は同部以外にも工業管理部や商務部、農村部など19の政府部門が管理しているため、国家発展改革委員会が事務局となり、中央政府(部)レベルのプラットフォームを構築し連携を図っているとの説明があった。
続いて、JTTRIの坂本渉研究員より「港湾と臨港産業」(原文は英語)と題して発表した。日本の港湾の種別、臨海部の産業立地など港湾の役割を概説した上で、政策課題と取組として、①ドライバルク船の大型化に対応した国際バルク戦略港湾政策、②産地と港湾が連携した農林水産物・食品の輸出促進と事例紹介、③地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備事例の紹介、④カーボンニュートラルポート(CNP)形成と洋上風力発電、⑤港湾における気候変動対応、について報告した。
質疑では、中国側より、臨港地区の産業配置や空間デザインは誰が行うのか質問があり、坂本研究員より、国(国土交通省)と地方政府(港湾管理者)による港湾計画の仕組みを説明した。また、港湾経済の特色として輸出入拠点化や物流コスト効率化、マルチモーダル化などの中国の課題を踏まえつつ日本の課題について質問があり、坂本研究員から、これらは日中共通の課題との認識を述べ、施策について補足的な説明を行った。

研究発表(賀振東研究員)

研究発表(坂本渉研究員)
■セッション2「都市圏の交通発展」
ICTから蒋中銘副研究員が「中国都市圏の交通発展と通勤効率化」(原文は英語)と題して発表した。まず、2020年の習近平国家主席の講話(中長期経済社会発展の国家戦略における重要課題)が指摘する「優位性ある地域への産業と人口の集中は経済の客観的な趨勢であるが、都市単体の規模拡大は限界があり、職住が平衡し交通利便性の高い近郊都市の建設と多中心化・郊外発展を進め、中心都市の人口や機能の過密問題を逐次解決すべき」の方針を踏まえ、①国家発展改革委員会が中心となり、南京、成都等で「都市圏発展計画」を省地方政府とともに策定し、「1時間通勤圏」を基本範囲とした都市整備を進めているとの紹介があった。(2023年データでは、主要都市で通勤時間60分以上の住民の割合は、北京市28%、上海市18%等)
このため、②「軌道交通を骨格とする都市圏」を目指し、幹線鉄道、都市間鉄道、郊外鉄道、市内軌道の「4つの軌道交通網の融合」に向け、東京や欧州都市も参考に推進しているとの紹介があった。
一方、③課題として、都市間路線バスでは行政区域を跨る路線審査や法令の標準化が進まない障害や、北京市内の8鉄道ターミナルと都市機能の配置とが一体化できていないといった問題を挙げながら、④都市圏の通勤効率化に向けた鍵として、中心都市の地方政府が中心となり、鉄道企業や周辺都市と協調し都市圏交通の一体化計画を共同作成するよう促進しつつ、中央政府は交通施設の建設・運営に対する資金支援を行っていく、との紹介があった。
質疑では、日本側より、「4つの軌道交通網の融合」について詳しい補足依頼があり、蒋副研究員から、地方政府が計画し中央政府の認可の下、軌道交通のサービス向上や時間短縮策に取り組んでいるとの説明があった。また、日本の都市鉄道整備の経緯から、既成の鉄道ネットワークを活用した乗換のシームレス化が重要との助言や、都市間路線バス運営の課題に対し、韓国で導入されているBRT等専用化による円滑化について提案があり、蒋副研究員から、都市間中距離バス路線における地方政府間の連携を促進していくとの説明があった。
続いて、JTTRIから金山洋一主席研究員・研究統括が「大都市圏の鉄道発展」(原文は英語)と題して発表した。東京圏を重点に、①明治政府から民間、国鉄による幹線鉄道と環状線の骨格路線形成の経過を概説した上で、②戦後の国鉄「5方面作戦」での緩急分離や地下鉄ネットワーク整備、③民鉄による鉄道網整備として小林一三モデル(民鉄によるTOD)を紹介し、さらに、④相互直通運転の進展、第三セクター会社等による鉄道整備(つくばエクスプレス、みなとみらい線)と都市開発、政府審議会答申による整備の推進を紹介した。次いで、⑤鉄道整備スキームの進展として上下分離を採りあげ、建設・運営リスクと役割の官民分担、都市鉄道等利便増進法(2005年施行)に基づく神奈川東部方面線の整備について紹介し、最後に、総括として経緯から得られる鉄道整備に係る知見を紹介した。
質疑では、中国側より、中国の都市化も落ち着き後半期に入るなかで、既存のインフラをどう活かすべきか質問があり、金山統括から、高層化も含む都市空間の活用と交通施設との連携について説明があった。これに対し中国側からも、例えばCBD地区に位置する北京東駅を交通ネットワークハブとして高度利用していきたいとの発言があった。また、中国の不動産開発が厳しさを増すなか、過去に同じ課題に直面した日本の経験からTODの推進に対する質問があり、金山統括から、つくばエクスプレスでの宅鉄法による区画整理などについて説明を行った。
また、鉄道サービス向上の費用の旅客負担や、脱炭素化に向けて道路交通から鉄道への需要転換を図るための整備費用の負担について質問があり、金山統括から、鉄道会社自身の負担だけでなく、輸送力増強投資に対する公的支援を導入した整備制度について説明した。

研究調査発表(蒋中銘副研究員)

研究調査発表(金山洋一主席研究員)
■セッション3「緊急物流(緊急物資輸送)」
ICTから芦越副研究員が「緊急物流システムの構築-経緯、現状、展望」(原文は英文)と題して発表した。緊急物流の定義として、「突発的な事態に対し国民の生命財産を確保し、災害被害を軽減するため物資や人員、資金や情報を緊急に調達・輸送・分配する物流活動」との説明に続き、①2003年SARS流行時の物資混乱を教訓とした緊急物流の省庁横断チーム設立、2008年汶川地震における国務院チームによる統一指揮、2018年の「国家応急管理部」設立による体制確立について紹介があった。②現在は、国家応急管理部による中央政府12部門への指揮体制の下、物資備蓄として中央政府30か所、各省2-3か所、各市1か所、企業備蓄庫1か所の協調備蓄制度を運営するほか、物資輸送では特に、大型無人機の幹線輸送や小型無人機による山岳地帯輸送、無人車など無人輸送技術の他、ラストマイルにおける社区居委員会やボランティアの参加の仕組みについて紹介があった。③課題として、多数の部門間での指揮・調整のプラットフォームの欠如、協力企業が負担する運賃や保管料などコスト回収の困難性が挙げられた。
最後に、④今後の方向性として、2026年までに企業参画や市民協働による社会的な緊急物流システムを構築し、EC産業や小売店舗の物資配布拠点の活用、参加した市民へのポイント制度による公共サービス交換などについて説明があった。
質疑では、日本側から緊急物流の定義と時系列について質問があり、芦副研究員から、事前の準備、災害発生時の初動輸送、復旧のための建設資材等供給を含む包括的な内容について補足説明があった。
続いて、JTTRIから榎本通也主任研究員が「大規模災害その他の危機における緊急物資輸送」(原文は英語)と題して発表した。①東日本大震災において官民挙げて実施した陸海空の緊急物資輸送や、交通インフラの早期復旧の取組について紹介しました。日本では交通運輸・物流事業とも国土交通省が所管し、トラック事業者団体に対し緊急輸送の協力要請を行う一体的な官民連携体制が整えられている点を補足した。
②現在の仕組みとして、国が自治体の要請を待たずに行う「プッシュ型支援」の流れと、災害対策基本法に基づく物資の調達・輸送に関わる各省庁の役割を紹介し、③能登半島地震の緊急物資輸送では、リレー輸送と物資輸送拠点において、物流事業者のノウハウや資機材を活用した荷捌きや輸送の効率化や、(公財)日本財団が実施した船舶による海上物資輸送等を紹介した。
最後に、④継続的改善に向けた国土交通省の施策として、課題である市町村避難所への3次輸送(ラストマイル)の体制強化に向けて、地方運輸局の相談窓口を通じた市町村と物流事業者との協定締結や連携訓練の実施支援や、ITによる物資調達・調整支援システムの改善と自治体向け研修の展開について紹介した。
質疑では、中国側より、国家応急管理部のような専門家チームの強化について質問があり、榎本研究員より、日本において中央・地方政府とも、危機管理全体の対応部門と専門性を持つ職員の強化は途上の課題であるが、緊急物資輸送に限れば、プロである民間物流事業者の活用が有効であり平時における連携協定の準備に力点を置いていることを紹介した。また、能登半島地震で県広域物資拠点となった産業展示館の平時の用途について質問があり、コンベンションホールとして整備され、平時は物産展示会等で使用され大量の物資搬出入に適していること、災害専用倉庫ではないことを紹介した。

研究調査発表(芦越副研究員)

研究調査発表(榎本通也主任研究員)
■閉会挨拶
JTTRIの屋井鉄雄所長から、3つのテーマを通じ、運輸交通分野における「インテグレーション」(統合)の視点から日中両国の共通点と相違点について深く議論し知見を共有できたことへ、中国側への謝意を表明した。第1セッションでは、交通・物流と産業との融合、港湾を取り巻く新たな課題に対応する主体間の協力について、第2セッションでは、中国大都市圏の将来ビジョンとなる4つの鉄道ネットワークの統合、東京圏の鉄道整備の過去と未来の統合について、第3セッションでは、両国共通の課題となる緊急物流の平時と有事の統合、国と地方政府の統合対応について共有し、各テーマのインテグレーションの進展に期待し、日本側の閉会挨拶を行った。
最後に、ICTの李連成所長から、日本が先行した高い経済社会水準と、運輸経済の整備や新たな課題への挑戦は中国にとって学ぶべき価値が大きく、新しい状況・技術・要請への対応、特に高齢化・少子化は喫緊の課題であり、2021年に人口ピークアウトし6人に1人が65歳以上の高齢化社会を迎え、AI技術に着目していると紹介があった。近年、中国の運輸交通水準は現代化し躍進してきたが、中国政府は運輸交通を先進的・戦略的産業と位置付け、スローガンに掲げる「人はお出かけを楽しみ、物は優れた物流システムに恵まれる」の実現に向け、一衣帯水の隣国である中日双方の専門家が引き続き議論と交流を深めることを期待し、中国側の閉会挨拶を行った。

閉会挨拶(屋井鉄雄所長)

閉会挨拶(李連成所長)
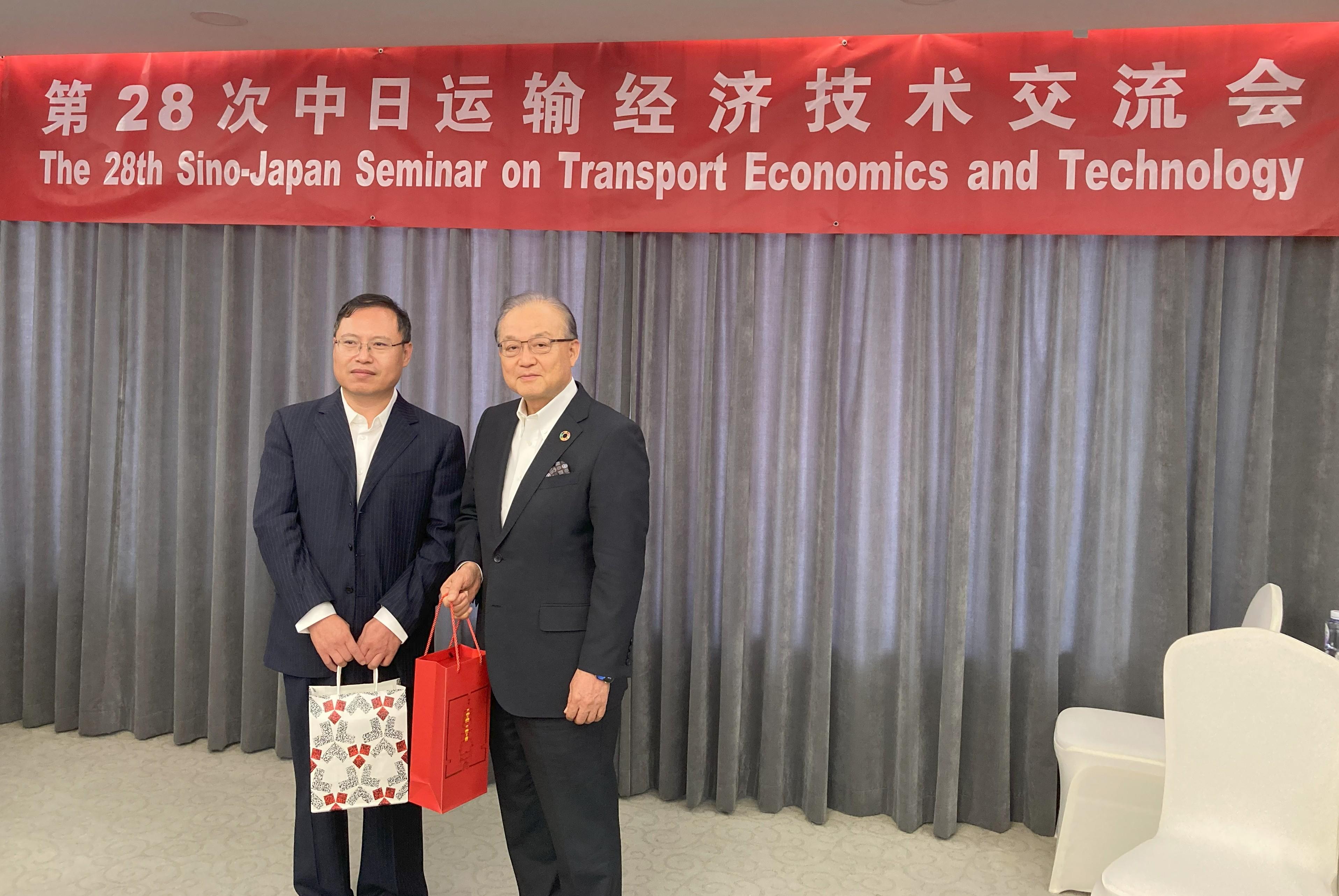
記念品交換(宿利正史会長、李連成所長)
■現地見学会
ICTのご案内により、23日は北京市軌道交通指揮センターを訪問した。同センターは北京市交通委
員会(市政府の一部門)の直属組織であり、北京市内の地下鉄計18路線(番号線)、郊外鉄道及び空港線11路線の全29路線、総延長879km(2025年8月)に及ぶ北京市軌道交通の運行指令を担う数か所のセンターの一つである。職員より2つの大型モニターによる運行管理の「見える化」について説明頂いた。「路線図」モニターでは、日本と同様、列車の運行管理状況が表示され、一方の「運行指標」モニターでは、リアルタイムでの乗降人数や、1時間単位の予測人数の推移や断面乗車率が一覧できるなど、ITによる先進的なデータ管理がなされていることが特徴的であった。
25日は、北京西駅を訪問した。北京市内8か所の地上駅・基幹ターミナルの一つであり、高速鉄道(G)、都市間鉄道(C)や動力列車(D)、普通列車(K、T等)計約20路線の発着を担い、1日平均18万人の旅客が出発。近年は地下鉄の北京西駅との上下の乗換利便性が大きく向上した。
また、両日は地下鉄の乗車体験を行い、一部の路線で運行されている自動運転車両に乗車した。

北京西駅
地下鉄車両(自動運転車両は撮影不可)
ICカードタッチ及びQRコードの決済対応改札


