2025年度「日本交通学会研究報告会」への参加報告
- 他機関との交流


| 日時 | 2025/10/4(土) 〜 5(日) |
|---|
2025年10月4日~5日に、第84回日本交通学会研究報告会が専修大学神田キャンパス(東京都千代田区)で開催され、当研究所から6名(前研究員を含め7名)が参加しました。
日本交通学会は、1941年設立の東亜交通学会が前身で、交通政策の課題について交通経済学を中心として研究する学会で、交通経済学に関心のある研究者、交通工学の専門家・研究機関をはじめ、官庁や事業者など約470から構成されており、運輸総合研究所は継続して特別会員になっています。毎年秋に研究報告会を開催し、学会機関誌(交通学研究)などを発行しています。学会会長は、現在の竹内健蔵氏(東京女子大学教授)から太田和博氏(専修大学商学部教授)に交替することとなりました。なお、日本交通学会の第11代会長及び第16代会長は、それぞれ、運輸政策研究所(現在の当研究所)の第3代所長の杉山武彦氏(一橋大学名誉教授)及び第4代所長の山内弘隆氏(武蔵野大学経営学部特任教授・一橋大学名誉教授)が務めていました。次回研究報告会は2026年10月3及び4日に近畿大学東大阪キャンパス(大阪府東大阪市)で開催される予定です。
当日の結果
10月4日は、午前中に特別セッション「鉄道運賃セッション」が開催されました。冒頭に、〇山内弘隆氏(武蔵野大学経営学部特任教授 当研究所評議員)から、「鉄道運賃制度等のあり方に関する勉強会」(一橋大学・エコモ財団寄付講義)について、鉄道事業者等は参加するものの各組織から独立して開かれたこと、問題提起を行うための提言を行った旨等の説明がありました。続いて、〇当該勉強会に参加した菅生康史氏(当研究所研究員)が、当該勉強会の成果として、趣旨、議論(・鉄道が社会にもたらす効果・鉄道の運営効率化や利便性向上に関するこれまでの取組み・鉄道を取巻く事業環境の変化・消費者庁、金融業界等による鉄道運賃に関する考え方)の概況及び提言内容(参考としての運賃体系及び運賃水準に関する制度案を含む。)を報告しました。続くパネルディスカッションでは、上記報告を受けて、パネリストの〇田邉勝巳氏(慶應義塾大学商学部教授 当研究所研究アドバイザー)、〇原田峻平氏(名古屋市立大学データサイエンス学部准教授)、〇岩崎真也氏(東海旅客鉄道株式会社執行役員 総合企画本部副本部長・経営管理部長)及び〇五島雄一郎氏(東急電鉄株式会社経営戦略部統括課長)から順次発表があり、その後、〇手塚広一郎氏(日本大学経済学部教授、経済学部長)によるコーディネートの下で、パネリストによる議論が行われました。例えば、原田准教授は、・一旦上がった運賃等についてデフレなどで費用が低下した際には下げる仕組みが必要ではないか、・東京名古屋間の新幹線の料金が仮に上がった場合、独占利潤ではないかと疑問が出る可能性があり、サービスに見合った対価であると実務的にどのように理解を得るのか、という旨の問題提起をされました。
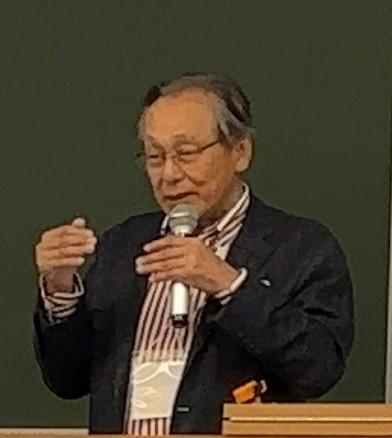
(山内教授)
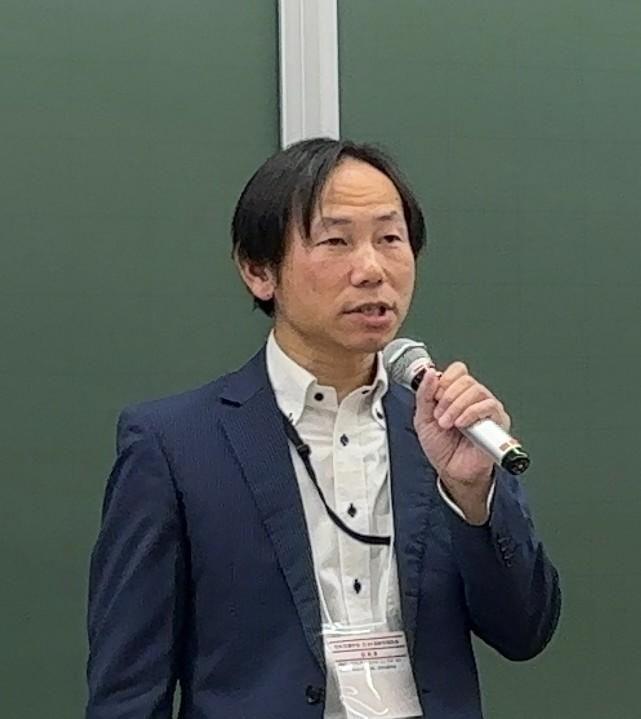
(菅生研究員)

(田邉教授)

(原田准教授)
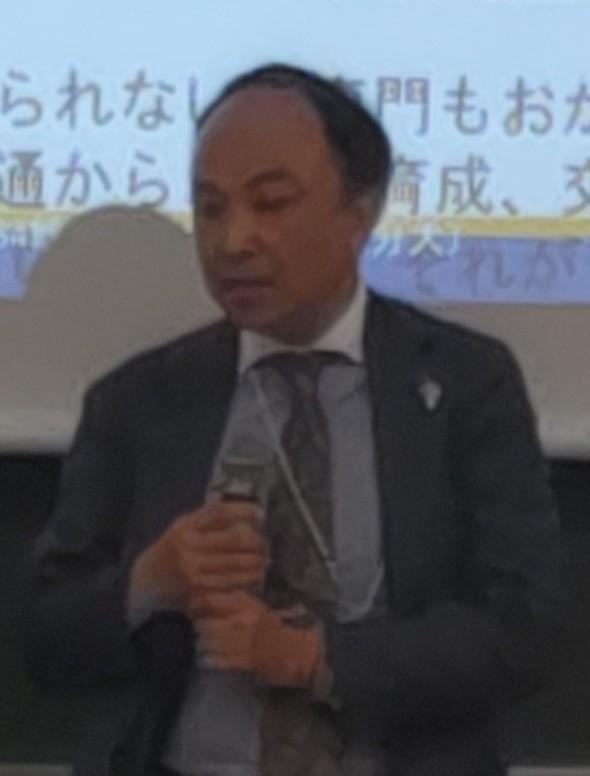
(大井教授)
同日午後は、統一論題シンポジウム「学問と政策の関係を問う」では、〇太田和博氏(専修大学商学部教授)からの趣旨説明に続き、〇山内教授からの基調講演が行われました。また、山内教授に加えて、〇髙橋愛典氏(近畿大学経営学部教授)、〇大井尚司氏(大分大学経済学部教授 元当研究所客員研究員・研究員)、〇岡野まさ子氏(国土交通省大臣官房総括審議官兼物流統括調整官)がパネリストとして参加して、太田教授コーディネーターによる論点(・審議会の役割、・大学(教員)からの関わり方、・交通経済学専門家の必要性)の下で、パネルディスカッションが行われました。なお、大井教授は、当研究所で研究員等として携わった際に、官民及び土木系との接点ができたことが後の政策形成への貢献活動の大きな基礎になった旨を紹介されました。
また、同日の総会では、2025年度日本交通学会賞として、著書の部:重谷陽一『非対称競争下における競争戦略:寡占市場でLCCはいかに生き残ったのか』(文理閣、2025年2月)、論文の部:森山真稔・安達晃史「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」(『交通学研究』第68号、2025年3月)の受賞決定が報告されました。
翌5日は、午前と午後に亘って、自由論題研究報告の6セッションが開かれました。セッションC(公共交通)では、後藤佑司氏(神戸大学博士後期課程)等が「過疎地域における路線バスとデマンドバス:事前予約の与える影響」と題して報告発表を行いました。この発表は、徒歩時間、乗車時間及び予約締切時刻の3要素に着目してデマンドバスと路線バスの利便性を評価する計量モデルを構築し、予約締切時刻がデマンドバスの利便性に及ぼす影響について考察しています。これに対し、島本真嗣氏((株)建設技術研究所大阪支社道路・交通部グループ長 前当研究所研究員)が討論を行い、上記3要素を選定した理由等について質問しました。
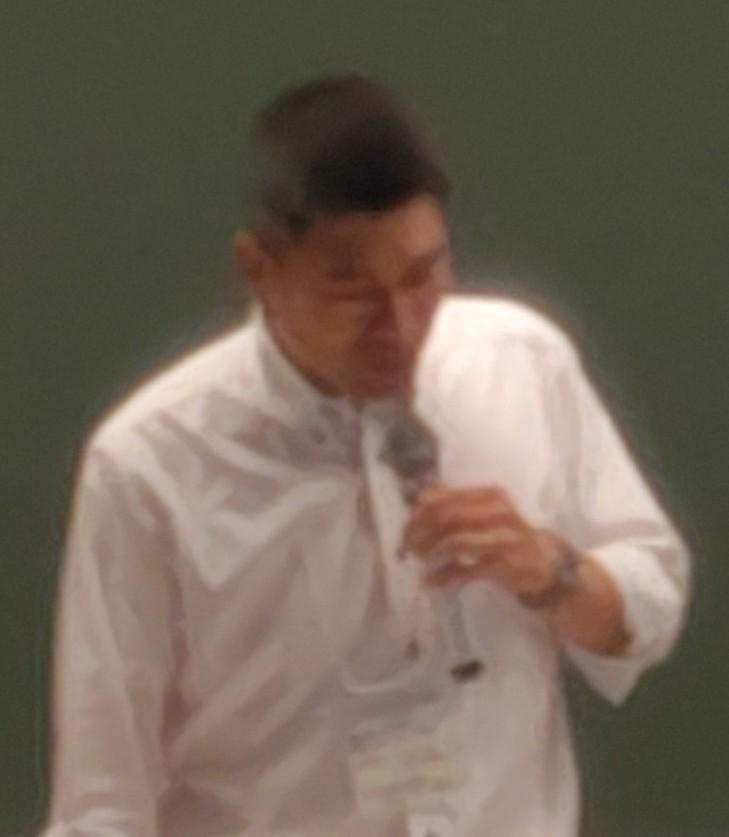
(討論する島本前研究員)
(山内教授)
(菅生研究員)
(田邉教授)
(原田准教授)
(大井教授)
同日午後は、統一論題シンポジウム「学問と政策の関係を問う」では、〇太田和博氏(専修大学商学部教授)からの趣旨説明に続き、〇山内教授からの基調講演が行われました。また、山内教授に加えて、〇髙橋愛典氏(近畿大学経営学部教授)、〇大井尚司氏(大分大学経済学部教授 元当研究所客員研究員・研究員)、〇岡野まさ子氏(国土交通省大臣官房総括審議官兼物流統括調整官)がパネリストとして参加して、太田教授コーディネーターによる論点(・審議会の役割、・大学(教員)からの関わり方、・交通経済学専門家の必要性)の下で、パネルディスカッションが行われました。なお、大井教授は、当研究所で研究員等として携わった際に、官民及び土木系との接点ができたことが後の政策形成への貢献活動の大きな基礎になった旨を紹介されました。
また、同日の総会では、2025年度日本交通学会賞として、著書の部:重谷陽一『非対称競争下における競争戦略:寡占市場でLCCはいかに生き残ったのか』(文理閣、2025年2月)、論文の部:森山真稔・安達晃史「航空旅客輸送事業における機材編成と効率性」(『交通学研究』第68号、2025年3月)の受賞決定が報告されました。
翌5日は、午前と午後に亘って、自由論題研究報告の6セッションが開かれました。セッションC(公共交通)では、後藤佑司氏(神戸大学博士後期課程)等が「過疎地域における路線バスとデマンドバス:事前予約の与える影響」と題して報告発表を行いました。この発表は、徒歩時間、乗車時間及び予約締切時刻の3要素に着目してデマンドバスと路線バスの利便性を評価する計量モデルを構築し、予約締切時刻がデマンドバスの利便性に及ぼす影響について考察しています。これに対し、島本真嗣氏((株)建設技術研究所大阪支社道路・交通部グループ長 前当研究所研究員)が討論を行い、上記3要素を選定した理由等について質問しました。
(討論する島本前研究員)


